第5回 「1~2歳児のママへ」編1
子どもが子どもでいられる時間は長いようで、とてもみじかいものです。
「いい親」になろうとがんばりすぎず、焦らず、
お子さんと一緒に1歩ずつ、楽しみながら進んでください。
(内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より)
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―「楽習」
コミュニケーション力を育てたいなら「ごっこ遊び」を一緒に楽しんで!
子どもは1歳半くらいで、おもちゃのお茶碗にご飯を入れて食べるまねや、おもちゃの茶器でお茶を入れて飲むようなしぐさをすることがあります。
これが「ごっこ遊び」のはじまりです。大人のしていることを観察して、その動作をまねします。「お茶を入れる→お茶を飲む」という流れを作りだしています。
このとき、想像力が養われるのです。 ごっこ遊びをするようになると、紙を丸めてお皿に並べて大人に「ハイ」と渡すときもあります。
大人は 「あら、おいしそうね」とそれを受け取り、「パクパク」と食べるふりをすると、子どもも満足します。
子どもは大人がどんな対応をするのかも想像しているのです。子どもは喜んで、何度も紙のお団子を勧めるでしょう。
大人が関わることで、どんどん世界が広がります。 2歳半ごろになると、ごっこ遊びがさらに発展していきます。
それまでは「お茶を入れる」というひとつの動作を繰り返していたのが、「お客さんが来たとき」という場面を設定して、その流れの中で「お茶を入れて勧める」
という動作が出てきます。 やがて友だちと一緒に同じ世界を共有できるようになると、お父さん、お母さんなどの役割が生まれて、子どもが何を演じるのかをはっきりと意識するようになります。
これがままごと遊びです。
ままごとはひとりではできません。親しい友だちと即興で会話を作り出し、時には話の進行に食い違いがあってケンカをしたりしながら、まさにコミュニケーションの基本を身につけていくのです。
このように何げなくしているように思われるごっこ遊びも、想像力を育むのに大切な役割を担っています。
そして、想像力が広がると人との関わり方も考えられるようになり、コミュニケーション能力も育ちます。
子どもにとっては遊びが何よりも大切だということが、わかるのではないでしょうか。
me[ミー]秋号2015 autumn Vol.28より転載
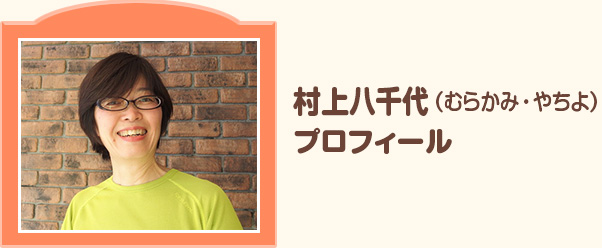
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



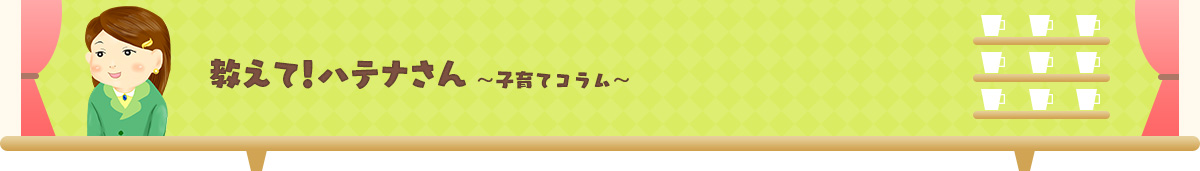
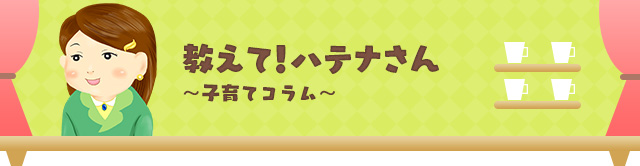

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]