第10回 2歳頃から多くなる「独り言」。思考が育っている証拠です。
知って納得!子どもの脳の成長編
親がいくら教えても、子どもがその通りにできない時はできないものです。
子どもが親の言うことを聞かないのにも理由はあります。親にとってはマイナスに思えることも、
実は子どもが成長していくための大切なプロセスでもあるのです。
(内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―
今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを
内田先生がやさしく解説してくださいます。
脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、
子育ては一層たのしいものになることでしょう。
独り言は、2歳になったころから多くなります。
親御さんの中には「何か病気なの?」と悩んでしまう人もいるようですが、その心配はいりません。
一人で遊んでいるときに「これはこっちに置いて、これはどこにしよう」とおもちゃの配置をかえたり、クレヨンで絵を描いているときに「赤がないなあ、じゃあ、黄色を使おう」と言ったりするのは、声を出すほうがうまく考えをまとめられるからです。
子どもは独り言を言うことで自分自身に質問し、答えています。やがて言葉を発しなくても心の中で自問自答するようになります。独り言は、心の中で言葉を使って思考するようになるまでのプロセスのひとつなのです。もしこの内なる言葉が育たなければ、子どもは何かを想像することも、記憶することもできないでしょう。
文字を書けるようになっても、最初のうちは「ここをまっすぐ」という具合に声を出さないと書けない子どももいます。また、「あ」と言ってから“あ”を書くというように、一字ずつ声に出して唱えながら文字を書きます。言葉が手の動きを支えているのですね。
独り言は3歳以降に集団生活をするようになるとさらに増え、7、8歳になると急速に減っていきます。独り言を言いながら、自分の想像に集中しているときは、無理に入り込まずにそのままにしておきましょう。この時、心の中でどんどん言葉が育っているはずです。
me[ミー]夏号2015 summer Vol.27より転載
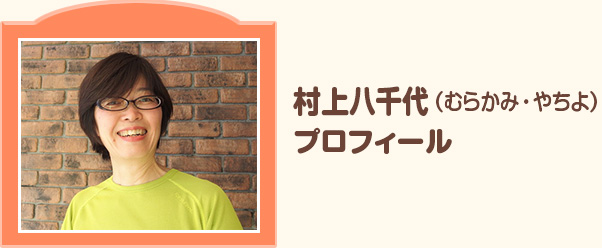
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



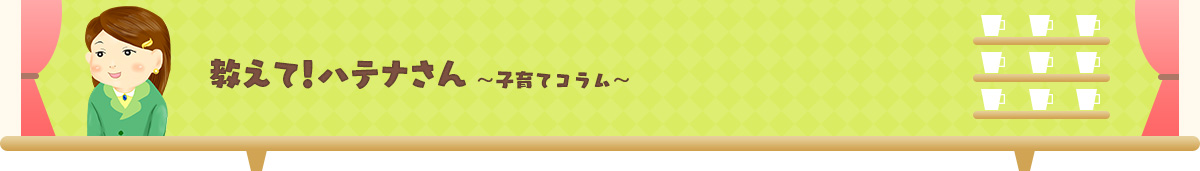
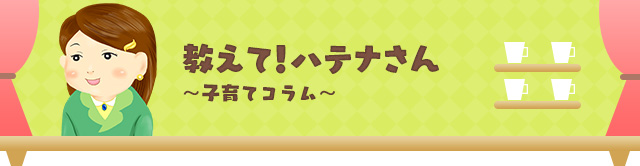

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]