第13回 「図鑑型」の子どもと「物語型」の子ども 編1
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―
今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを
内田先生がやさしく解説してくださいます。
脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、
子育ては一層たのしいものになることでしょう。
子どもにはそれぞれ、もって生まれた「気質」「性格」があります。
以前、私の研究室で、生後10か月の赤ちゃん80名を対象にして、犬型ロボットのアイボを使った研究をしたことがあります。
プレイルームで子どもとお母さんに遊んでもらっているときに、アイボを赤ちゃんのそばに置いて動かすと、どの赤ちゃんもはじめはビックリしたような顔で見つめています。しかしその後の反応は、2つに分かれました。
1つは「お母さん、これ何?」という表情をして、そばにいるお母さんの顔を不安げに見上げました。このタイプの子どもは、80人中48人いました。
残りの32人は、アイボに釘づけになっていました。このときの赤ちゃんは「おもしろそう!」というような好奇心いっぱいの表情をしていました。
面白いことに、その後1歳半のときに同じ実験を繰り返しても、それぞれの人数の比率は変わりませんでした。どうやら、赤ちゃんのころから「気質」「性格」というものはある程度できているようです。
私は、最初にお母さんを見た子どもを「物語型」、アイボに興味を引かれてじっと見つめた子どもを「図鑑型」と呼んでいます。
物語型は人間関係に敏感で、言葉も「おはよう」「こんにちは」など、挨拶や感情を表現する言葉から覚えていきます。
図鑑型はモノやモノの成り立ちや動きに興味を持ち、「おっこちた」「なくなっちゃった」「ピーポピーポいってる」などの動詞も覚えます。また、物の名前もたくさん覚えるのです。
どちらがいい悪いという話ではなく、子どもにはそれぞれの個性があるということです。
「おぎゃあ」とこの世に生まれたときは泣いてばかりでどの赤ちゃんも同じように感じるかもしれませんが、その内側ではしっかりと個性が育まれているのですね。
me[ミー]夏号2016 Summer Vol.31より転載
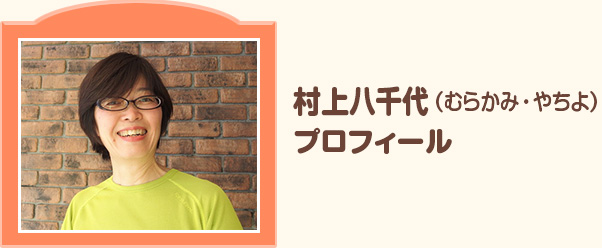
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



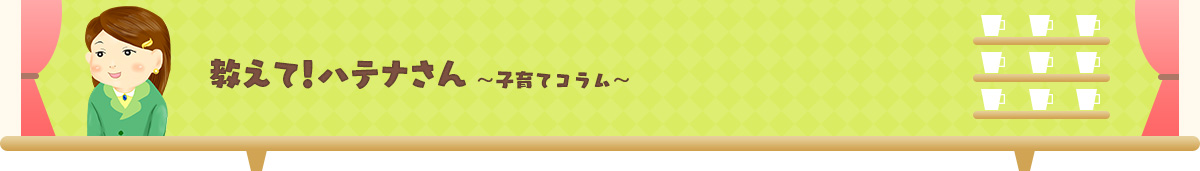
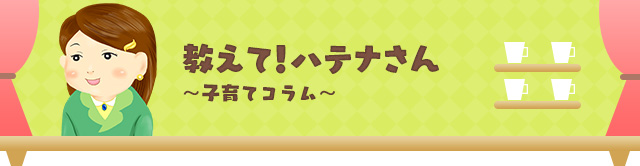

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]