第16回「絵本でこころの栄養補充」1
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―
今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを
内田先生がやさしく解説してくださいます。
脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、
子育ては一層たのしいものになることでしょう。
赤ちゃんには「読み聞かせ」ではなく、本と「遊ぶ」感覚を大切に
絵本は0歳の赤ちゃんから大人まで、誰もが楽しめるものです。赤ちゃんにとって、絵本と出会うのはとてもうれしい経験です。赤ちゃんは、絵本に触り、めくり、引っぱり、ときにはなめたり、破ったりします。絵本は「本」ではなくて、楽しいおもちゃの一つなのです。
赤ちゃん向けの絵本はイラストや写真が大きくハッキリしていて、色も単純なものがいいでしょう。食べ物や動物、乗り物など、身近なもので、子どもの興味を引くようなものが描かれている絵本がおすすめです。赤ちゃん向けの絵本は、絵だけで文字が載ってないものが多いので、お母さんの中には「これでは読みきかせられない」と思う人もいるかもしれません。
最初のうちは、絵本をめくって絵を見るだけでもいいと思います。読み聞かせるよりは、遊ぶという感覚を大切にしましょう。絵本の筋に関係なく、「おっきなワンワンだね」「おめめがパッチリしているね」と話しかけたり、「ぽんぽん」「どーん」「ふわふわ」「とんとん」などリズミカルな言葉をつけてあげると、赤ちゃんはおもしろがります。少し大きくなってきたら、言葉の響きを大切にしながら、しっかりと読み聞かせをしてあげましょう。「大きな桃がどんぶらこ、どんぶらこと流れていました」「大判、小判がざっくざく」
このように、リズミカルな言葉を繰り返す表現は、子どもも覚えやすく、すぐに「どんぶらこ」とまねするでしょう。お話の途中で、絵のほうに寄り道しても構いません。「ちょうちょうが飛んでるね」「赤い服と青い服だね。靴とぼうしはおそろいね]などと、子どもと言葉を交わしながら、読み進めると、子どもは絵本をより楽しめるに違いありません。
me[ミー]秋号2016 Autumn Vol.32より転載
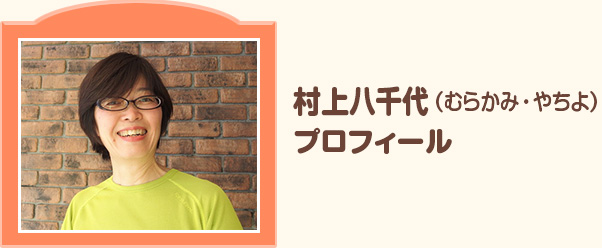
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



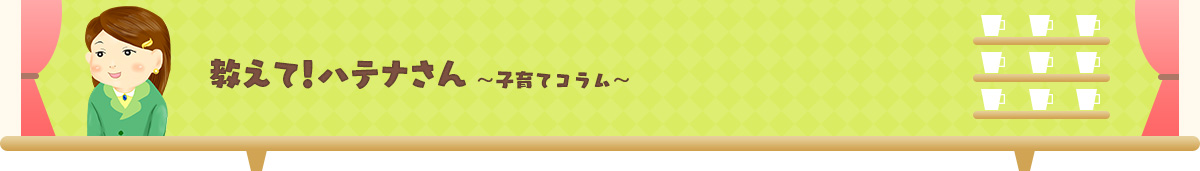
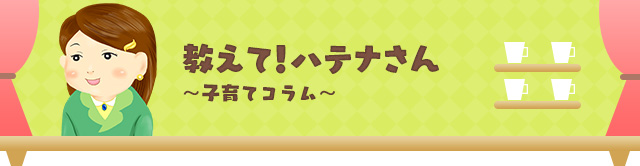

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]