第17回「絵本でこころの栄養補充」2
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―
今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを
内田先生がやさしく解説してくださいます。
脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、
子育ては一層たのしいものになることでしょう。
4歳になると物語世界を楽しめるように
ただし、4歳になったら解説を加えずに、絵本の文章だけを読み聞かせるようにしましょう。そのほうが、集中して一つの物語世界を頭の中で構築できるからです。
5歳ぐらいになると、『大きなカブ』のように繰り返しの文章を好むようになります。子どものお気に入りの絵本が見つかると、「もう一回読んで!」とせがまれると思いますが、何度でも読んであげましょう。子どもにとって絵本との出合いはとてもうれしい経験。お気に入りの絵本ができるのは、喜ばしいことです。
ベッテルハイムという児童精神科医が、『昔話の魔力』という本の中である子どもの例を紹介しています。その子どもは注意欠陥・多動性障害という症状があり、じっと座っていられずにうろうろと歩き回ったり、ちょっとしたことでかんしゃくを起こす傾向がありました。色々な治療をしてもまったく効果がなかったそうです。ある日ベッテルハイムが、病室に数冊の絵本を持って入ったら、その子どもは、ふっとこちらを見ました。そこで、「読んであげようか?」と絵本を読み聞かせてみたら、普段は少しもじっとしていられない子どもが、少しも動かずに聞いていたのです。ベッドに座って絵を見つめ、ベッテルハイムの声にじっと耳を傾けていたそうです。次の日も、また次の日も、その子は同じ絵本を選びました。それから毎日同じ絵本を読み聞かせ、1ヶ月経ってその絵本を味わい尽くしたのか、次の本に移っていきました。そのようなことを繰り返しているうちに、その子どもはかなり落ち着いてきて、症状が改善されたそうです。本が治療の糸口になったのですね。
子どもは、同じ本でも、そこから受け取っている心の栄養は、毎日毎日違っているのでしょう。昨日とは違った感触を味わいながら、毎日新しい発見をしているはずです。その本を卒業するまで繰り返し読み聞かせ、子どもの心に充分に栄養を与えてあげてください。
me[ミー]秋号2016 Autumn Vol.32より転載
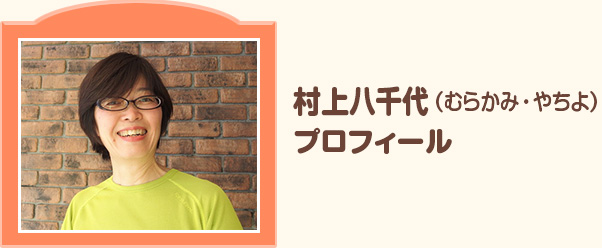
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



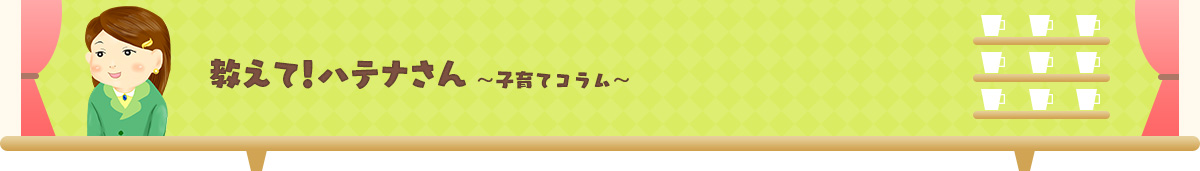
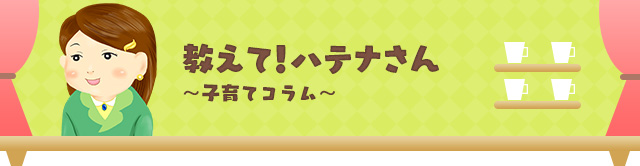

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]