第18回「絵本でこころの栄養補充」3
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―
今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを
内田先生がやさしく解説してくださいます。
脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、
子育ては一層たのしいものになることでしょう。
絵本は、親から子へ受け継ぐ「心の栄養」
読み聞かせをするときは、テレビを消して、子どもがお母さんの声に集中できるようにしましょう。
何より絵本の読み聞かせは、お母さんと子どもが心を通い合わせるチャンスです。お母さんの声を聞きながら、絵本の世界へ入っていく。それは二人だけで共有できる幸せな時間なのです。
私自身の一人娘の子育て経験を少しお話しさせていただきます。模範となるような子育てはしてこなかった私ですが、できるだけ心がけ、実行してきたことがあります。それは娘に対して、幼い赤ちゃんのころから一人の人として敬意を払い、大人に対するのと同じように、いやそれ以上に、その人格を大事にして付き合ってきたつもりです。共に人生を歩んでいく人として、より高いもの、より美しきものを一人占めするのでなく、彼女と共有したいと願い、実行してきたように思うのです。そしてもう一つ心がけたのは、平和を願う心の涵養でした。彼女には、“二度と戦争を起こしてはならない”という願いをもち、平和な世界を築くことに努力を惜しまない意志をもてる大人になってほしいと願い、思春期の頃には広島平和記念資料館や長崎の平和祈念館などを一緒に訪れました。親子とも、涙し、言葉もなく、ただただ戦争の悲しさと恐ろしさを前に佇む旅でした。
絵本の読み聞かせは、乳児期から児童期の終わりまで、ずっと続けてまいりましたが、平和教育につながる本は彼女の成長に応じて用意しました。小学校の頃には、松谷みよ子の『ふたりのイーダ』やアンネ・フランクの『アンネの日記』、さらに高校時代にはヴィクトール・フランクルの『夜と霧』なども読み合い、話し合いました。
0歳の赤ちゃんから大人まで、誰もが楽しめる読み聞かせの時間を通じて、親から子へ、次の世代へ大切な心の栄養が受け継がれていくことを願ってやみません。
me[ミー]秋号2016 Autumn Vol.32より転載
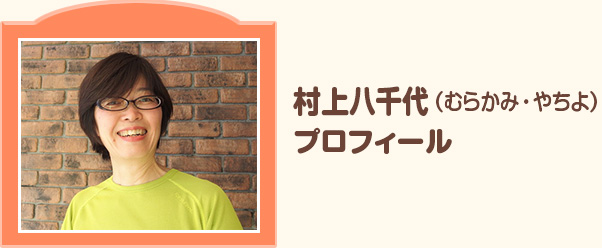
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



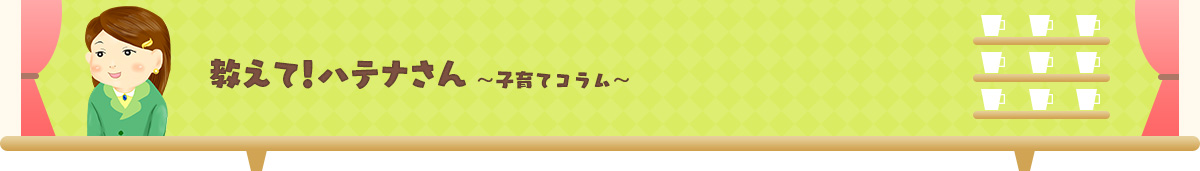
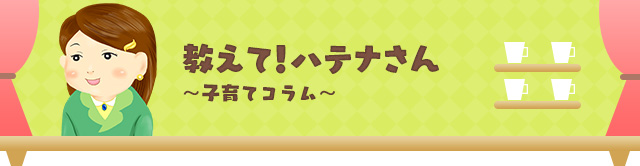

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]