第20回「テレビとの上手な付き合い方」編2
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―
今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを
内田先生がやさしく解説してくださいます。
脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、
子育ては一層たのしいものになることでしょう。
(お悩み)
『子どもがテレビを見ている間は静かなので、ついついテレビに子守をさせてしまいます。テレビはやっぱり子どもに悪影響を与えてしまうのでしょうか?』
子どもは二つのことに集中できません。食事中はテレビを消しましょう。
テレビは、「ほどほど」が一番です。ぜひ、小さいころからテレビとの上手な付き合い方を身につけるようにサポートしてあげましょう。
まず、子どもは二つのことに注意を向けられませんから、テレビを見るときはテレビに集中できる環境を整えます。たとえば食事中にテレビがついていると、そちらに気をとられて箸が止まってしまいます。食事中はテレビを消すこと。そのためにはお父さん・お母さんもテレビをつけっ放しにしないようにしましょう。
こういう話をすると、「子どものために楽しみを奪われる」と嘆く親がいるのは残念なことです。大人は見たい番組をビデオに録って、子どもが眠った後にゆっくりと気兼ねなくみることをお勧めします。
何より、テレビを消すと子どもとの会話が生まれます。親が子どもといっしょに過ごせる時間は長いようでいて短いので、いまいっしょに過ごす時間を最優先してほしいと思います。
また、テレビ番組は親が選んであげる必要があります。まだ情報処理の力がない子どもに望ましい番組としてのポイントは、次の3点です。
1.画面がシンプルであること
2.子どもの生活に関連したテーマを扱っていること
3.言葉がはっきりしてゆっくりしたテンポであること
ただし、子どもはテレビだけでは知識を習得できません。子どもは体験してみて、はじめて学習できるのです。
子どもはテレビを見ているときはお母さんもいっしょに見るように心がけ、子どもが画面を指さして興味を示したら、黙ってうなずくか、「ブーブーね」「かわいいニャンニャンね」などと、子どもの反応を受け止め、共感するような言葉をかけてあげるとよいと思います。ただ画面を見ているだけでは、それが何なのか理解するまで時間がかかります。
テレビも使い方によっては親子のコミュニケーションを生む道具にもなるのです。効果的に活用していきましょう。
me[ミー]冬号2017 Winter Vol.33より転載
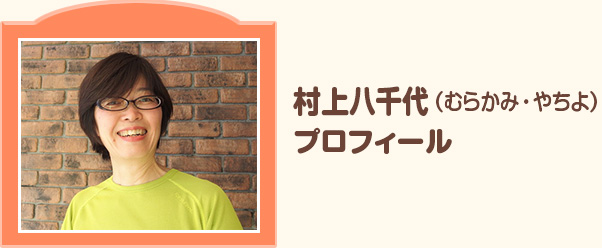
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



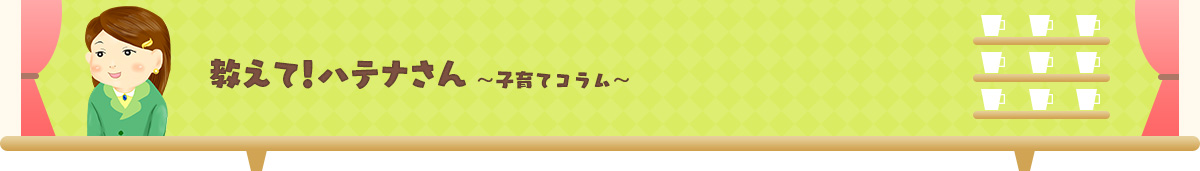
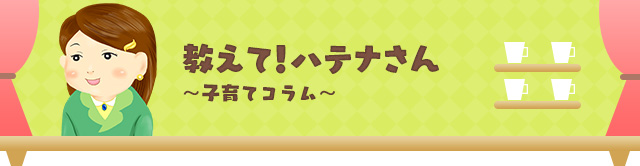

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]