第21回「テレビとの上手な付き合い方」編3
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―
今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを
内田先生がやさしく解説してくださいます。
脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、
子育ては一層たのしいものになることでしょう。
(お悩み)
『子どもがテレビを見ている間は静かなので、ついついテレビに子守をさせてしまいます。テレビはやっぱり子どもに悪影響を与えてしまうのでしょうか?』
スマホが親子のコミュニケーション時間を奪っていませんか?
今回いただいたご相談は「テレビの視聴」についてでしたが、最近では、「スマホ子守」という言葉も聞かれるほど、子育て中の親のスマートフォンへの過度な依存も問題視されています。
子ども向けのアプリだからといってスマホを子どもに持たせたまま長時間画面を見せ続けるような使い方は、やはりテレビと同様に、赤ちゃんの心身の発達にとってよくない影響を与えてしまいます。
確かに、スマートフォンやパソコンは情報を得るためのツールとしても、コミュニケーションのツールとしても非常に便利で有用な道具ですので、親御さんがスマホを手放せない気持ちはよくわかります。子どもが泣き止むようなアプリもあったりするので頼りたくなる気持ちもわかります。しかしながら、その利便性の裏に潜むスマホ特有の弊害もあることを認識し、子育て真最中の親御さんはとくにその使い方に注意を払う必要があります。
乳幼児のお母さんがスマホに多くの時間を割いてしまうと、たとえ同じ時間や空間を赤ちゃんと共有していても、お母さんの注意は画面に集中してしまい、赤ちゃんの姿が目に入りません。赤ちゃんの目を見て、声をかけたりあやしたり、様子を見守ったりする母と子の大事なコミュニケーションの機会が奪われてしまうのです。
公園の猫に気づいた赤ちゃんがびっくりしてお母さんに「あれなに?」の問いかけの表情を向けたとしても、スマホに気を取られているお母さんは「大丈夫、ニャンニャンよ」と答えてあげることができません。
また、「ママ、みて!」と自分でつかまり立ちのできた赤ちゃんが、得意げにお母さんの方を向いたとしても、スマホに夢中になっているお母さんは気づくことができないかもしれません。そのとき、赤ちゃんはどんなに残念な気持ちになるでしょうか・・・。親としても、赤ちゃんの日に日に成長していく瞬間を見逃してしまうことほど勿体無いことはありません。
スマホの中の情報は待ってくれても、子どもの成長は待ってはくれません。スマホはぜひ脇に置き、「すごいね!たっちできたのね!」というように、子どもといっしょに笑顔になれる瞬間を、これからも沢山つくっていってください。
スマホもテレビも、それ自体が子どもの発達に悪影響を与えるものではありません。親が主体となって、子どもといっしょに楽しむような応答的な関わりの中で、上手に取り入れていきましょう。
me[ミー]冬号2017 Winter Vol.33より転載
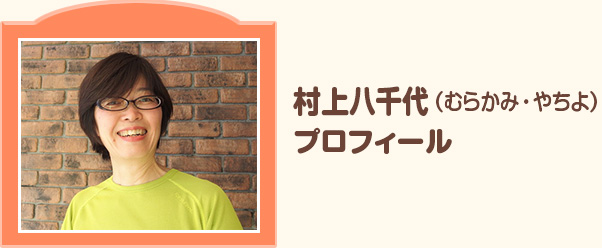
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



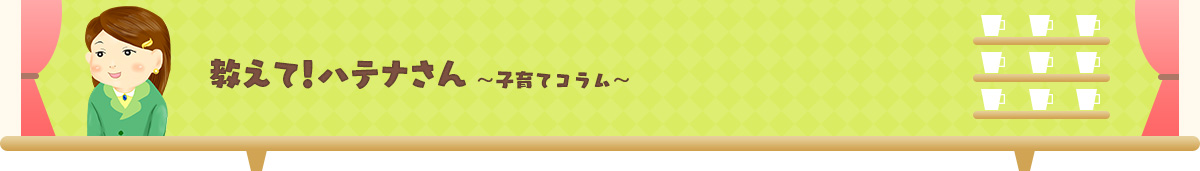
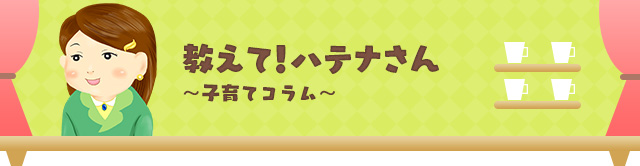

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]