便育コラム 第2回 お母さんは「うんちサイン」を五感でキャッチ
お母さんが家庭でオムツを交換する場合と、保育士さんが保育園でオムツを交換する場合を比較したことがあります。
お母さんが子どもの「うんちサイン」を受け止める方法はとっても多様です。
モジモジする子どものしぐさや、重たそうなオムツの形や、においや、オムツの中を触った感触や、子どものぐずりや子どもからの申告など、実にいろいろな情報を、目で見て、鼻で嗅いで、耳で聞いて、手で触って、うんちが出ていないかどうかを確認しようとします(味覚を使った確認方法はさすがに見かけませんでしたが(笑))。
一方、保育園では一人の保育士さんが複数の子どものオムツを交換しなければならないこともあって、活動の節目に定期的に一斉にオムツを交換するなどの方法を取っている場合が少なくありません。
お母さんは複数の方法をあれやこれややってみて「うんちサイン」を受け取りますが、保育士さんはオムツの外から触ってみたり、オムツの中を直接のぞいたり、より的確な方法でスピーディに確認します。
つまり、お母さんは子どもが発信する「うんちサイン」をくまなく受け取ろうとしていて、保育士さんはいわば効率よく「うんちサイン」を受け取っているともいえます。
私たちはいつもと違う子どものしぐさなどを見ると、「あれ、うんちが出たからかな」とか、「なんか、力んでるみたい」などと自然に意味づけしようとします。
子どもは「うんちサイン」に多様に反応してもらえることで、オムツの気持ち悪さや、うんちが出る感覚などを、よりはっきりと自覚できるようになってゆきます。
大人の意味付けと子どものサインがマッチすると、「通じあった」という充実感が双方に生まれます。
この時期の子どもは言葉がまだまだ未熟ですが、このようなやりとりによってコミュニケーションをふかめてゆきます。
そして気持ちを読み取ってもらえることがわかるようになると、より読み取ってもらえる大人の前ではよりアピールしてくれるようになるわけです。
お母さんの「うんちサイン」の確認のしかたは、時には自分の鼻をオムツの外側にあててにおいを嗅いだりすることもあります。
お母さんはオムツを交換するついでに、ついつい赤ちゃんのぷっくりしたおなかに顔をうずめたくなることだってあります。
お母さんが「うんちサイン」を確認するときも、オムツを交換するときも保育士さんと比べると密接にからだとからだが触れ合うことが多いのです。
そして子どももお母さんもこれが気持ちよいのですね。
オムツ期の子どもはとっても濃密でしあわせな時間を過ごしているといえるのです。
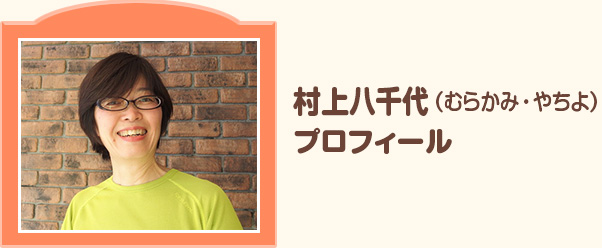
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



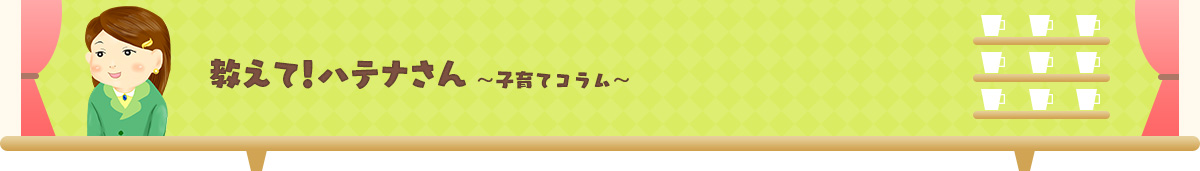
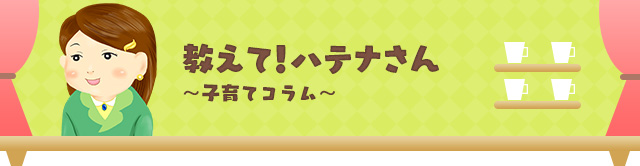

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]