便育コラム 第3回 なぜヒトは「おむつ」を使うのか?
考えてみれば子育てに「おむつ」を使うのはヒトだけです。犬も猫も「おむつ」を使うなんてことはないですね。ヒトの親戚チンパンジーだって使いません。(飼育下にある動物に人間がつけることはありますが)
なぜヒトは「おむつ」を使うことになったのでしょうか。
それはヒトの子育てが「離れつつ保護する」という独特の方式をとっているからです。
ヒトの子育てが他の動物と決定的に違っていることはさまざまな「モノ」が母子の間に存在することです。
おむつの他に、哺乳瓶、人工乳、ベビーベッド、ベビーカートなどなどヒトが使う子育てグッズは数えきれないほど存在します。
これらの「モノ」は赤ちゃんを「離れつつ保護する」ことを可能にしているのです。
おむつはお母さんが見ていないところで赤ちゃんがうんちやおしっこをしても赤ちゃんがうんちまみれになったり、床や布団が汚れることを防いでくれます。
哺乳瓶はお母さんが留守にしていても別の人が赤ちゃんにオッパイを与えることを可能にします。そして人工乳を使えば母乳がなくても赤ちゃんを立派に育てることもできるのです。他の動物のオッパイをそのままではないにしても代用するなんて考えてみれば驚きですよね。
ベビーベッドは赤ちゃんが寝ている間にお母さんがそばを離れても安全に赤ちゃんを守ってくれます。
ベビーカートはお母さんが重たい思いをして赤ちゃんを抱えなくても安全に移動させることをサポートします。
これらの「モノ」はお母さんが赤ちゃんとぴったりくっついていなくても赤ちゃんをしっかり守れるように開発されたといってもいいでしょう。
赤ちゃんがベビーベッドでぐっすり眠ってくれた時のお母さんの解放感! つかの間の自由時間にお茶をゆっくり飲んだり、溜まっていた家事を片づけたり・・・とてもありがたい時間です。
これらの子育てグッズが無くては現代人の子育てはままならないほど、私たちの生活に溶け込んでいます。
しかし、この便利さと引き換えに現代人が忘れかけていることがあります。
それは身体で赤ちゃんを感じる感性とでもいいましょうか。
「モノ」が介在することでお母さんは赤ちゃんを四六時中抱きかかえている必要がなくなって、赤ちゃんのふとした動きで「オッパイが欲しいのかな?」とか「おしっこかな?」と身体で感じ取るのではなく、時計を見てミルクを与えるタイミングを決めたり、哺乳瓶の目盛りで与えるミルクの量を測ったり、おむつの表面の色表示で交換したりと、赤ちゃんが発するサインよりも「モノ」が示すサインを頼りにしてしまうことが増えていると思いませんか。
便利なものは活用して子育ての負担は減らしながら、こういうことも頭の片隅に留めておくことも大切な気がします。
参考資料:根ヶ山光一〈子別れ〉としての子育て(NHKブックス)2006年
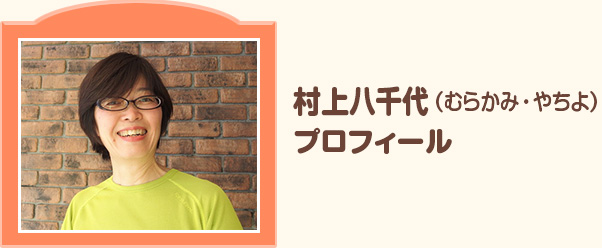
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



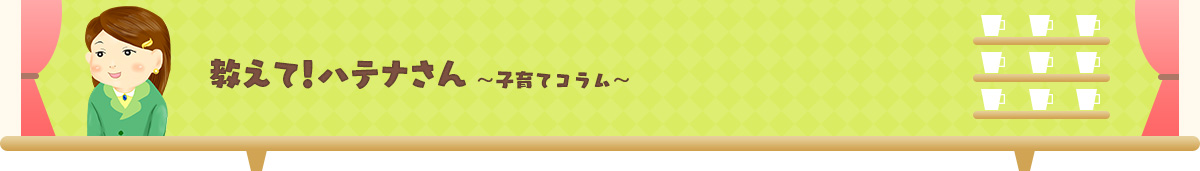
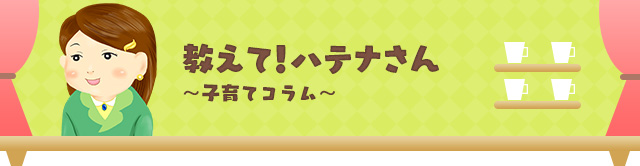

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]