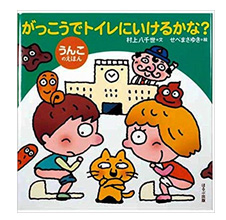便育コラム 第21回入学に備えて和式便器は練習するべき?
小学校への入学準備として、和式便器の使い方を習得しておくことが加えられるようになってから久しいですが、小学校には和式便器がまだまだ多いのです。
家庭や幼稚園・保育園で洋式便器を使い慣れている子どもにとっては和式便器で用を足すのを苦手に感じる子も少なくないでしょう。
大都市では公共トイレでさえも洋式便器が普及していますから、子どもが日常生活で和式便器を使う機会はなかなかないのが事実です。練習しておくようにと言われても練習できる適当なトイレを探すのもひと苦労です。
文部科学省の2016年の発表によると公立の小中学校の洋式化率は45.3%であり、まだ5割以上が和式便器なのです。小中学校のトイレを洋式へと切り替えることは各自治体が課題として取り組んでいますが、校舎の耐震化工事や教室のエアコン設置に追われ後回しになってしまっているのが現状です。
政令指定都市で小中学校の洋式化率が一番低い大阪府堺市では、136小中学校の洋式化率を10年かけて23%から60%以上にしようとしていますが、その予算は約100億円にものぼります。このように学校のトイレは数も多く、改修には莫大な費用と時間がかかることがわかります。
小学校に入学した児童が学校で和式便器を使えないのは、使い方を知らないということもありますが、「しゃがむ」姿勢が取れないことも大きな要因となっているようです。便器にしゃがもうとすると後ろにひっくり返ってしまいそうになるのです。足首などの関節が固いことが理由に挙げられるでしょう。
また和式便器にしゃがむときは洋式便器に腰掛けるのと比べて、衣服を上げ下げするのにコツを要します。下手をすると裾が床について汚れたり、衣服に排泄物が付着してしまう可能性が高いのです。
そして、和式便器ではしゃがむ位置に気をつけないと尿も便もはみ出してしまうという問題が起こります。
学校生活にまだ慣れない新入児童にとって、使いなれないトイレでの失敗はとてもストレスフルなのです。
小学校や保育園・幼稚園で「便育」講座を行っている筆者は、子どもたちが入学当初に学校のトイレで戸惑う様子を知って、事前に和式便器の使い方が楽しく学べる絵本のようなものがあればよいのにと考えて出版社に提案したことがありました。最初は「『和式便器の使い方』をテーマに絵本を作るなんて前代未聞だ」と難色を示されましたが、結局は増刷を繰り返すほどの売れ行きとなりました。
和式便器はどんな姿勢で使うのか、どこに足を置いたらうんちがはみ出ずに用を足せるのか、もしもうんちがはみ出したらどうしたらよいのか、用を足した後は必ず手を洗うこと、授業中にトイレに行きたくなったらどうしたらよいのかなどを簡潔にまとめました。さらに絵本の巻末には「れんしゅうトイレ(原寸大の和式便器のポスター)」を付け、家庭のリビングでも簡単に疑似練習ができるようにしました。
小学生の中には和式便器を使った際に便がはみ出したりすると、どうしてよいのかわからずそのまま放置したり、後から入った子どもに指摘されて恥ずかしい思いをする子どもや他児が汚した便器に遭遇して使うのを我慢してしまう子どもがいます。
子どもたちに和式便器の使い方を教えるときに忘れないでほしいのは、もしもはみ出してしまった時の対処方法などを教えておくことです。
自分で汚したところは自分で拭き取るなどの対処法を理解していれば落ち着いて行動することができるでしょう。トイレットペーパーで拭き取ること、万が一手に便が付いても石鹸を使って手を洗えば心配ないことなど改めて教えておくことが必要です。
学校によっては、便がはみ出た場合は衛生上の理由から自分で処理せずに教師に申告するように指導する方針を取っているところもあるようですが、それで本当に子どもを衛生的に守れるのかどうかは改めて考えなくてはならないと思います。
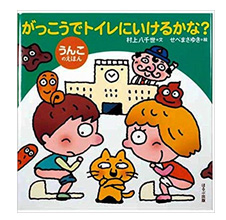 「がっこうでと入れに行けるかな?」ほるぷ出版
「がっこうでと入れに行けるかな?」ほるぷ出版
文:村上八千世 絵:せべまさゆき
 巻末付録:れんしゅうトイレ
巻末付録:れんしゅうトイレ
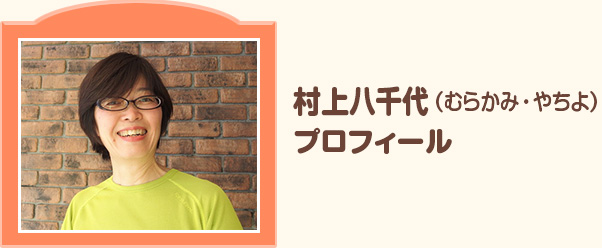
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



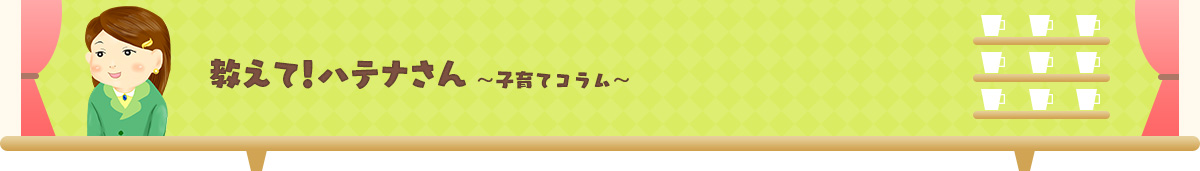
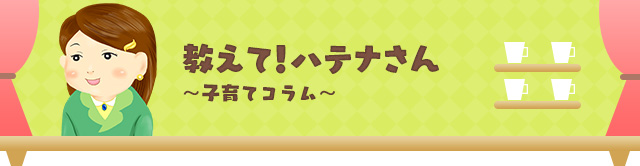

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]