便育コラム 第28回「便育」のすすめ 出前講座
筆者は1998年から小学校や幼稚園・保育園などで「便育」講座を行ってきました。
「便育」とはまず自分の大便について知るということです。
きっかけは「学校で大便をしない子どもたち」が多いという問題でした。
20年前は今よりももっと小学校のトイレは汚くて臭くて暗いトイレが多かったのですが、トイレを改修してきれいにしてもやはり学校では排便をするのを我慢する子どもが根強く残ったのでした。我慢の理由は他児からのからかいを敬遠してのことです。
排便に対するからかいについては「第20回 うんこといじめ」でも書かせていただきましたが、排泄に対する子どもたちのネガティブなイメージが根底にあると考えられます。
からかう側もからかわれる側も排泄行為を単に恥ずかしくて臭い行為だと認識していれば、からかいはエスカレートしてしまうでしょうし、排泄行為の大切さや意味を理解できていれば、からかう行為も調節が効くでしょう。
便育講座では最初、「排泄は恥ずかしいことではない」ということを子どもたちに訴えようとしましたが、一度恥ずかしくなってしまった子どもたちの認識を「恥ずかしくない」という認識に変えるのは難しいことでした。
そこでとにかく大便のことをもっとよく知ってもらおうと、国際規格を参考にして大便の分類を行い、ネーミングをしてみました。それが「うんぴ」「うんにょ」「うんち」「うんご」でした。タイプを見分けるときに色、形、ニオイをチェックすること、それぞれのタイプのうんこはどんなときに出るのか、どうすれば健康なときに出るうんこになるのかなど、子どもにもわかりやすく説明できるように考えました。
すると大便は臭くて汚くて、迷惑なものだと認識していた子どもたちが、「大便にそんな意味があるとは知らなかった。これからは自分の大便をよく見てみようと思う」というような感想を残してくれるようになったのです。
養護教諭の先生方からは「大便は『結果』なので、結果から生活を振り返ると説得力がある」という感想をいただきました。
子どもたちだけではありません。大人も意外に大便にどんなメッセージが込められているか知らないままで生きてきているのです。
知ってみると、大便を見て確めるのが面白くなります。
今日の大便を見て、食べるものや生活を変えてみると、次の日の大便には見事に変化が表われます。
自分の大便について知ることは、生涯病気になりにくい身体を手に入れることだと思います。
子どもにも大人にももっと自分の大便のことについて知ってもらいたいですね。
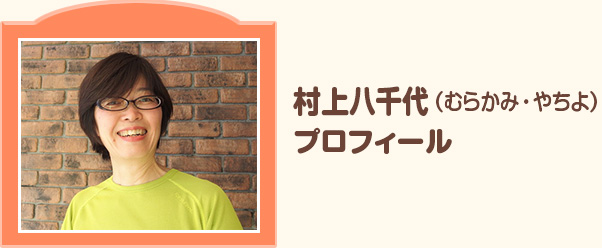
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



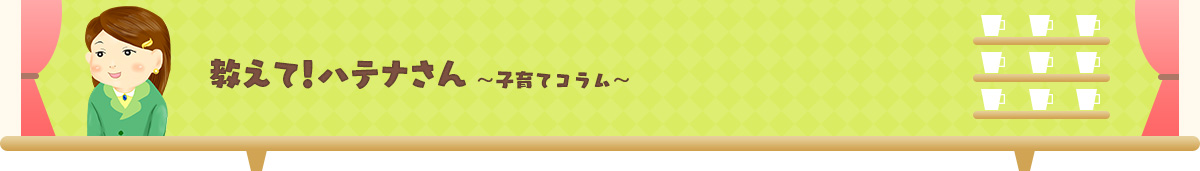
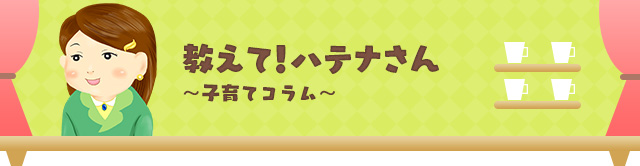

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]