便育コラム 第5回 「おむつはずし」と「おむつはずれ」
子どもが2歳を過ぎるころになると、「そろそろ、うちもやらなくちゃ」と焦るお母さんもいれば、「最近はゆっくりでもいいって言うわよね」とのんびり構えるお母さんもいて、果たしてどちらが正しいのか・・・・。
「トイレットトレーニング」というと、ある時を境に急に始めるようなイメージがありますが、それも変な話です。子どもの発達は何かが急にできるようには進まないからです。
他に「おむつはずし」とか「おむつはずれ」という呼び方もあります。
「おむつはずし」は親が主導の呼び方で、「おむつはずれ」は子どもが主導の呼び方といえるでしょう。最近は「おむつはずれ」がよく使われていますね。
親の都合で無理やり訓練を始めるのではなく、子どもの心身の準備ができてから、子どものペースに合わせて行おうという考え方を表しているようですが・・・・・。
ところで、私は保育園のトイレ環境の提案に関わることも多いのですが、0歳児クラス(※0歳児クラスには実年齢が2歳前までの子どもが在籍しています)では便器を保育室の中に設置するように提案することもあります。
その利点は子どもが座りたいときにすぐに座れることや、保育士さんがおむつを交換するすぐ横で便器に座らせることができることなどです。
このような環境の保育園では、「トイレットトレーニング」の時期を気にしなくなったという保育士さんの声を聞きます。
なぜなら、子どもが自主的におむつの外で排せつすることに興味を持てる「環境」があるからです。
以前は夏の初めになると、ある月齢以上の子どもは夏のうちにおむつを卒業させてしまおうと計画的にトレーニングを行っていましたが、トイレが保育室の中にできると子どもが座りたいときにトイレに座ることができるようになって「トイレットトレーニング」という言葉はだんだん使う必要がなくなってきたというのです。
子どもがトイレに座りたそうにしているのを見て、保育士さんがパンツを脱がせて座らせることもあれば、遊んでいる途中でモジモジしたり、動きがピタリと止まったり、しかめっ面をするなど子どもがサインを出したときに、それを読み取ってトイレに誘うこともあるようです。
そして、肝心なことは保育士さんが以前よりも子どもの動きやしぐさに敏感になってきたということなのです。「トイレに座りたい」「おしっこが出そう」という子どものサインを見逃すまいとする意識が強くなったというのです。
これは子どもと保育士さんがちゃんとコミュニケーションが取れているということを表しています。子どもが出したサインを保育士さんが受け取って、子どもが欲求を満足させるという関係がうまくできています。この結果、以前よりも一人でトイレに座ったり、おむつがはずれるのが早くなったのです。
「おむつはずれ」という子どもを中心にした表現の意図は本来こういうことではないかと思います。
しかし、間違った意味で理解されている場合も多いように思います。
「子どもがトイレに積極的に行きたがらなければ、しばらくおむつをつけていても大丈夫」というのは正しいでしょうか?
大事なのは子どもが出すサインをしっかり受け止められているかどうかなのです。サインを見落としたまま「うちの子はまだトイレには興味がないみたい」となってしまっては、まったくコミュニケーションが取れていないことになってしまいます。
ご家庭ならば、リビングにおまるを置いてみるのもよいですね。
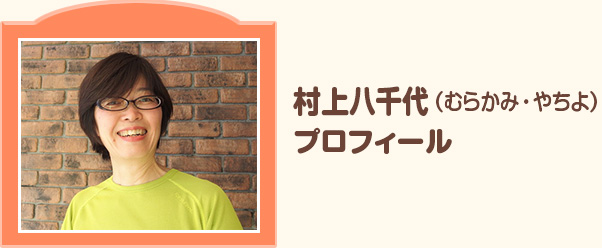
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



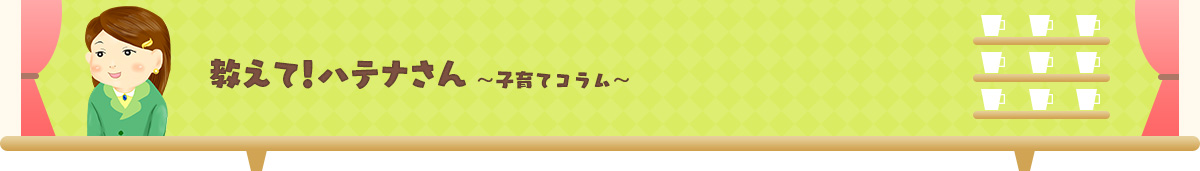
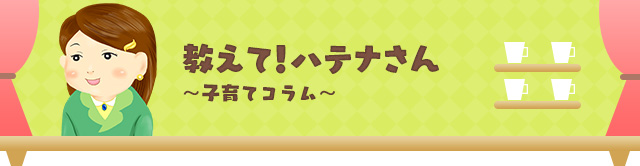

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]