第1回 「楽習」主体的な遊びを通して 子どもは伸びる
長年、教育の現場で多くの子どもたちとふれあい、
数々の調査研究を行われてきた内田先生。
今、日本の子どもたちに必要なものは、
“楽習”であるとお話ししてくださいました。
耳慣れない、この言葉。
いったい、どのようなものなのでしょうか?
子どもの学びにおいて、何よりも大切なこと。それは、〝主体性をもたせる〞ことだと話す内田伸子先生。「〝主体性〞などというと、少し難しく感じるかもしれませんね。言い換えれば、重要なのは〝playful learning〞の姿勢なんですよ。日本語に訳せば、〝楽習〞ですね。遊びの中で、たくさんの経験をさせること。それが、子どもの成長にはとても重要なんです。私は常々、大人が無理強いするのではなく、子ども自身が、『やりたい!』と思うような環境を整えてあげてほしいとお話ししています。みなさんも、自分のお子さんには積極的に生き生きと、たくさんのことにチャレンジしてほしいと考えていらっしゃるでしょう? そんな人間に育つために大切なのが、まさに 〝楽習〞 なんです」。 とはいえ、周りがお勉強の教室に通い出したり、スポーツ系の習い事をはじめたりなどの話を聞くと、「うちの子だけ、後れをとってしまうんじゃないかしら」と、焦ってしまうのも事実。子どもの好きなように、ただ遊ばせているだけなんて、何だか不安になってしまいます。
「まあ、その気持ちもわからないではないですが、それは〝その時だけ〞のできる、できないにすぎないのではないかしら」。子どものやる気を引き出し、たくさんの経験をさせる〝楽習〞。実は成長するにつれて、力を発揮してくるのだと内田先生は言います。
「国際的に実施されている、生徒の学習到達度を調べる、『PISA調査』というものがあります。少し前に、『フィンランドの算数の成績がとても優秀』なんて話を聞いたことがありませんか? それが、このPISA調査なんですが、実は日本は、算数の成績が、中国、韓国に差をつけられて、参加しているアジア諸国の中では最下位でした。算数に対する意欲が、日本の子どもはとても低いの。ちなみに文部科学省で行っている全国の小6、中3を対象にした学力テストでも、算数に関しては暗記的な問題だと平均80点は取れているのに、得た知識を応用して答えるような、自分で掘り下げていかないと解けない問題になると、正答率の平均がいきなり20点台に落ちてしまうんです。これ、どういうことを意味しているかわかりますか?
日本の子どもは、与えられたものに関しては機械的に対応することができるけれど、自分で意欲をもって取り組まなければいけない問題になってしまうと、一気に問題解決能力が下がってしまうということ。日本の子どもたちは、〝受け身〞の姿勢になってしまっているという実態が顕著になっているのです」。 与えられるものを、ただこなすだけになりがちな、今の日本の子どもたち。より積極的な姿勢にするには、どうしたらいいのでしょうか?
me[ミー]春号 2015 Spring Vol.25より転載
次回に続く…
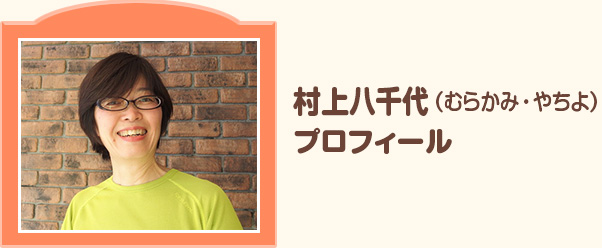
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



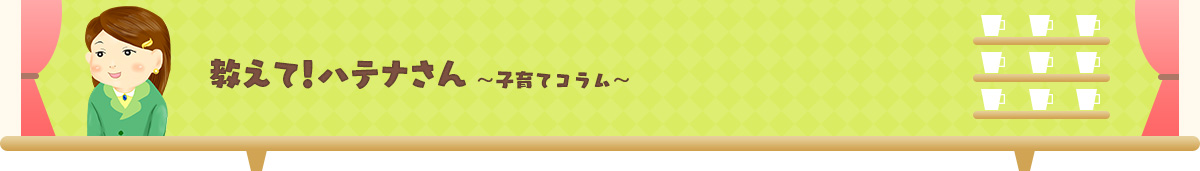
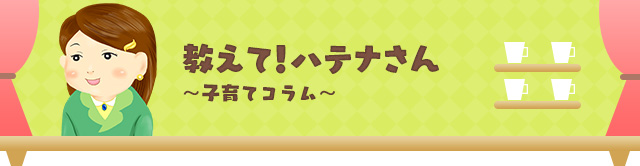

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]