便育コラム 第14回子どもが主体的になれるトイレタイムを
埼玉県さいたま市の浦和ひなどり保育園では0・1歳児保育室のトイレを園舎改築の折に保育室の中に設置しました。
改築前も保育室とトイレは引き戸一枚でつながっていましたが、トイレを使うことはありませんでした。
なぜならトイレの中に入ると保育室からは死角になって子どもから保育者の姿を見ることができず、保育者も子どもの姿を確認できないので一人でトイレに行かせることはできなかったからです。
それで当時は「おまる」をトイレの入り口(保育室側)に並べて、その「おまる」のすぐ前で保育者はおむつを交換したりしていました。
子ども用のトイレがすぐそこにあるのに、トイレを使わずおまるを前に並べて使うなんて変な話です。
しかし、その少しの距離に大きな違いがあったのです。
おまるに座る子どもと保育者が向かい合って座ることで、おまるの子どもはいつでも保育者と目を合わせることができます。保育者は手元で別の子どものおむつを替えながらおまるの子どもの様子を見て声をかけることもできるのです。
だから子どもは安心しておまるに座ることができ、好きなだけゆっくり座っていることができるのです。
子どもがおまるに座っている様子を見ていると、おしっこが出るのを不思議そうに眺めていたり、用を足し終わった後もしばらく座りつづけてぼーっとしていたりします。長いときは10分も20分も座っていることがあります。まるで自分の身体と対話しているようにも見えます。そして何か納得したようにおまるから立ち上がって保育者のもとに移動します。
このような時間は子どもの発達にとって大変重要だと思います。
おしっこが膀胱に溜まっている感覚、おしっこをしようと思って出すことができる感覚、おしっこが尿道を通って出てくる感覚、出終わって膀胱がしぼんだ感覚、膀胱がしぼんだ時は出そうと思っても出ないという感覚、そして自分で自分の身体をコントロールできるという感覚に気づき、納得のいくまでそれを味わっているのではないでしょうか。
浦和ひなどり保育園では0・1歳児クラスと2歳児クラスのトイレを保育室の中に設置しましたが、「トイレットトレーニング」というものをほとんど意識しなくなったと保育士の先生が話してくださいました。
子どもの主体性に任せたトイレタイムを保証してあげることで、子どもは自ら自律してくれるようです。
 【改築後のトイレ】保育室内にトイレを設置しているため、子どもは保育者に見守られながら用を足すことができる。(0・1歳児保育室)
【改築後のトイレ】保育室内にトイレを設置しているため、子どもは保育者に見守られながら用を足すことができる。(0・1歳児保育室)
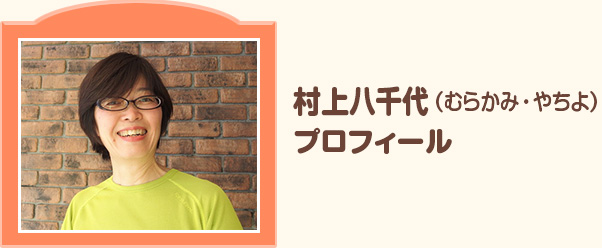
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



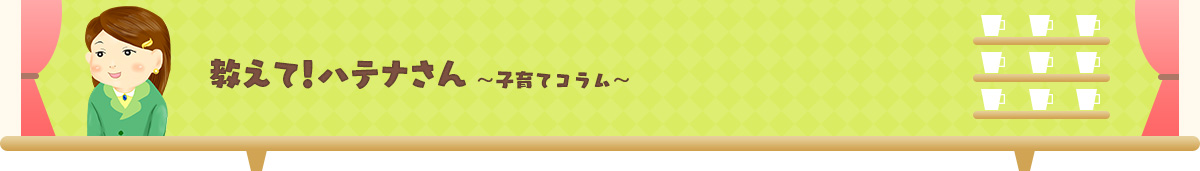
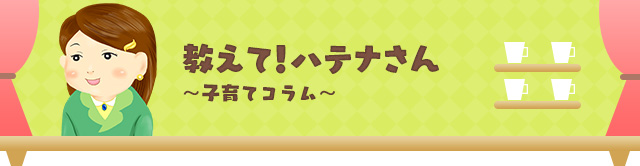

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]