便育コラム 第16回子どもたちが自分で考えて調整する環境
保育園のトイレを子どもたちが自由にアクセスできるようにすると、どんな変化があるのでしょうか。
「第15回 自由にトイレに行けると自立が早くなる!」でご紹介した大阪のおおわだ保育園の1・2歳児クラスのトイレでの事例を見てみましょう。
2歳児は以前は汽車のように隊列を組んで一斉にトイレの中まで行きましたが、改修後は子どもたちのペースでトイレに行くようになりました。
急いでいる子はさっさと便器に座り、急いでいない子はおしゃべりしながら待っています。
自分たちのペースで行くと、押し合ったり、順番でもめることも少ないようです。
以前は便器の前に並んで待っていましたが、今は並ばなくてもお互いに調整しあってうまく流れてゆきます。
保育者はトイレの中までついてゆかなくてもよいので離れて見守っています。
いざこざも起こらないので、指示や注意もなくなりました。
指示に従って子どもが動いていた時とは全く雰囲気も時間の流れ方も違うトイレタイムに生まれ変わったのです。
1歳児は月齢によって発達に開きがあります。用足し行動においても、月齢の大きい子はパンツを履いたままでトイレに来て、便器の前でサッとおろして用を足せます。一方月齢の小さい子は保育室で全部脱いでからトイレにやってきて用を足します。
便器への座り方も月齢が大きい子は大人と同じように便器を背にして座ることができますが、月齢の小さい子はそのまま便器を跨いで座ります。その方が身体が安定するからでしょう。
この時子どもたちはどんなふうに便器に座るか自分の能力に合わせて自分で考えて調整しているのです。
月齢の大きい子どもの様子を見てまねたり、いろんな座り方を熱心に試すこともあるようです。
ある子どもは便器に座ったと思ったら、一瞬で立って戻ってゆき、ある子どもはとっても長い時間便器に座っています。
それぞれ納得する時間もやり方も全く違うのです。
大人が必要以上に手や口を出さない環境では、子どもたちは自分で考え、納得するまで試してみて、充実した時間を過ごしていることがよくわかります。
 <改修前>
<改修前>
便器の前に並ばされる子どもたちと指導する保育者。子ども同士で押し合うこともよくありました。
 <改修後>
<改修後>
子どもたちは自分たちで調整し合って、順番に便器を使っています。なごやかなおしゃべりタイムでもあります。
 <改修後>
<改修後>
同じ1歳でも、発達段階は月齢によって差があって、トイレの使い方もこんなに違います。
右の子は月齢が小さいので便器に向かって座るのですが、このあと左の子のやり方を真似て座りなおします。
 <改修後>
<改修後>
子どもは便器に長く座っていても、保育者とアイコンタクトができるので安心していられます。
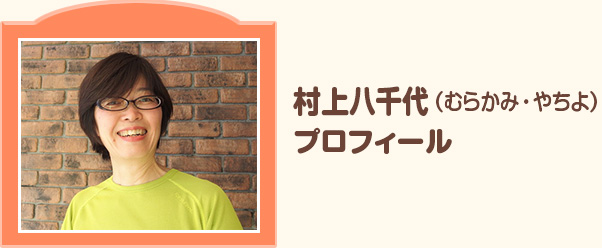
 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]



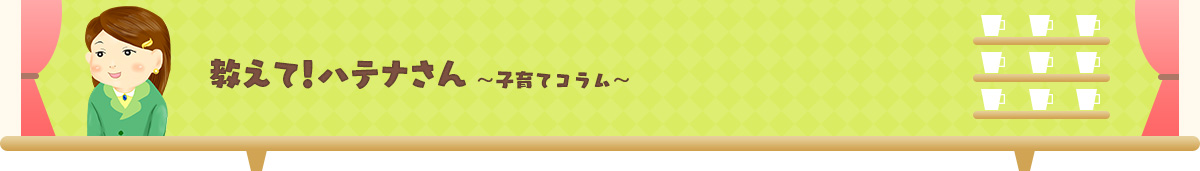
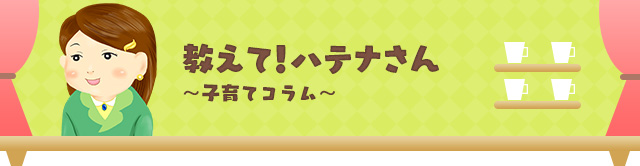

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]


