記事一覧
「絵本の読み聞かせは子育てによいときくけれど、何か心がけることはあるの?」 内田伸子先生のお話をご紹介します。 絵本は0歳の赤ちゃんから大人まで、誰もが楽しめるものです。子どもにとって絵本と出会うのはとても嬉しい体験です。 赤ちゃんにとっては、その絵本に触り、ひっぱり、時にはなめたり、破ったり…絵本は「本」ではなく、楽しいおもちゃの一つです。 赤ちゃん向けの絵本は、絵だけで文字が載っていないものが多いので、「 … 続きを読む 特別コラム「絵本でこころの栄養補充」
小学生が恥ずかしがって学校で大便できないという問題に興味を持ってから、かれこれ20年以上「便育」活動を行ってきました。 「大便」は大きな便りと書くように、身体からのメッセージだと子どもたちによく説明します。大便の「いろ」や「かたち」や「におい」にはそれぞれ意味があるということを理解してほしいと考えています。 (第23回うんこは生活のアウトプット) 子どもたちの多くは排便した後に自分の便を見ないで流してしまいま … 続きを読む 便育コラム 第32回「便育」で体調も人間関係も良好に
これまで30回にわたって子どもと「うんち」について書かせていただきました。今回と次回はその総括編とさせていただきます。 乳児期の子どもにとって「うんち」は単なる排泄物ではなく、特別なものです。 乳児期はうんちをすることで褒めてもらえ、それによって自分の存在意義を確認することもあります。 (第1回 うんちはプレゼント!) 「うんち」をしたあと、おむつを交換してもらったり、パンツを履かせてもらうこと … 続きを読む 便育コラム 第31回子どもにとって「うんち」はただの排泄物ではない
「う・ん・ち」(福音館書店)は動物などのうんちの図鑑で、さまざまな生き物のうんちの特性を詳しく説明しています。 この絵本を読んでいると、動物のうんちも虫のうんちも、ヒトのうんちと共通していることに気がつきます。動物や虫のうんちの色や形やにおいにも意味があるのです。 ライオンのうんちは格別に臭いそうなのですが、それはライオンが肉食だからでしょう。ヒトも肉食に偏るとうんちが臭くなります。 アゲハチョ … 続きを読む 便育コラム 第30回「うんち」のえほん紹介2 生き物のうんちの色や形には意味がある
私がまず一番にご紹介したい絵本は獣医師の竹田津実さんが書かれた「森のお医者さん⑦ うんちとおしっこのひみつ」(国土社)です。著者がご自身で撮影された写真と温かなまなざしで語った動物の様子がとってもほほえましいのです。 その中にキタキツネの親子のお話が出てくるのですが、母ギツネは子ギツネのおしりをきれいになめて子ギツネが排泄物で汚れないようにします。また子ギツネは母ギツネになめてもらわないとうんちができないのです。 &nbs … 続きを読む 便育コラム 第29回「うんち」のえほん紹介1 キタキツネの親子のお話
筆者は1998年から小学校や幼稚園・保育園などで「便育」講座を行ってきました。 「便育」とはまず自分の大便について知るということです。 きっかけは「学校で大便をしない子どもたち」が多いという問題でした。 20年前は今よりももっと小学校のトイレは汚くて臭くて暗いトイレが多かったのですが、トイレを改修してきれいにしてもやはり学校では排便をするのを我慢する子どもが根強く残ったのでした。我慢の理由は他児 … 続きを読む 便育コラム 第28回「便育」のすすめ 出前講座
子どもの排泄行為が自律すると、親の関心は子どもの排泄の有無や、いつどんな便を出しているのかということからすっかり遠ざかってしまいます。 そしてそれまでは子どもが便をするたびに「いいのが出たね」「がんばったね」と褒めていたのが、今度は子どもが「うんこ」の話をするものなら「汚いからやめなさい」「恥かしいからだめ」などと「躾」が始まります。 子どもが時と場合を考えずに不用意に排泄の話を人前でしないように躾けることは大事なことなのですが、排泄の … 続きを読む 便育コラム 第27回「うんこ」の話題をオープンにしよう!
おならには音の出るおならと出ないおなら、ニオイが臭いおならと臭くないおならがありますよね。 どんなときにどんなおならが出るのか考えたことはありましたか? おならも大便と同じように食べたものや生活によって「出かた」が変わるのです! おならも身体からの立派なメッセージなのです。 肉食の後のおならは臭くなることが多いです。動物性たんぱく質が腸内で分解されるときに出るガスが臭いニオイの元になっています。 … 続きを読む 便育コラム 第26回おならの音とにおい
外出先でトイレに入ると個室内に「音消し装置」が設置されているところが少なくないですね。これは主に女性が排泄中の音を他者に聞かれたくないという理由で洗浄水を流しながら用を足すようになったことがきっかけになっています。多くの女性が自分の排泄音をカモフラージュするために水を沢山流すので水道料金がかさんでしまうため、節水目的で「音消し装置」が開発されたのでした。 子どもが自分の排泄時の音を恥ずかしいと感じ始めるのは小学校の中学年以 … 続きを読む 便育コラム 第25回排泄時の音が気になる?
ところで快便のためにはぜひ行いたいことが5つあります。 <1.朝ご飯を食べる> 朝ご飯を食べると内臓が刺激され、胃や腸が動き始めて前の日に食べたものを直腸へと押し出します。内臓が刺激されることで脳や身体も目覚めます。 <2.野菜を食べる> 繊維が豊富な野菜をバランスよく摂取することで腸の中で大便は程よくまとまり排泄しやすくなります。繊維には栄養分はほとんどありませんが、排泄物のカサを増やして出やすくしてくれる … 続きを読む 便育コラム 第24回うんこダスマン! 5つの術!
前回はうんこのネーミングについてお話をしました。 「うんぴ」はおなかをこわした時に出る下痢の状態のことです。ドロドロで硫黄のようなニオイです。色は黄色っぽいことが多いです。「うんぴ」が出たら、冷たいものを食べ過ぎなかったか、古くなったものを食べなかったか思いめぐらしてみて、おなかを温かくして安静にします。 「うんにょ」は下痢ほどではないけれど柔らかくて、ニオイもちょっと臭い便のことです。「うんにょ」をよく見る … 続きを読む 便育コラム 第23回うんこは生活のアウトプット
ヒトも動物も食物を摂取するとともに排泄をしなければ生きてゆくことはできません。食べ物が栄養となって身体の一部となり、活力となって生活を支えるためには、口から取り入れた食べ物が消化・吸収され要らないものは身体の外部に排出される必要があるのです。 「食べること」と「排泄すること」は一体となった営みであるにもかかわらず、現代人は「食べること」には一生懸命注目しても、「排泄すること」からはとかく目を逸らそうとすることが気になります … 続きを読む 便育コラム 第22回うんこのネーミングで健康状態を知る
小学校への入学準備として、和式便器の使い方を習得しておくことが加えられるようになってから久しいですが、小学校には和式便器がまだまだ多いのです。 家庭や幼稚園・保育園で洋式便器を使い慣れている子どもにとっては和式便器で用を足すのを苦手に感じる子も少なくないでしょう。 大都市では公共トイレでさえも洋式便器が普及していますから、子どもが日常生活で和式便器を使う機会はなかなかないのが事実です。練習しておくようにと言われても練習でき … 続きを読む 便育コラム 第21回入学に備えて和式便器は練習するべき?
小学生が学校で排便を我慢するという問題を前回取り上げました。 子どもが学校で排便を我慢する理由には、トイレ環境が汚いことなどが大きな理由となっていますが、それだけではなく、「排便行為」がからかいやいじめの対象になりやすいということも一因となっています。 生きているものは誰でも排便をするにも関わらず、なぜそれがからかいの対象になるのでしょうか。 まず「からかい」について考えてみましょう。「からかい … 続きを読む 便育コラム 第20回うんこといじめ
20年ほど前に国内の小学校のトイレの使用状況を調査したことがありました。東京、福岡など15か所の小学校が調査対象でしたがどこも家庭のトイレの快適さとは程遠く、汚くて臭くて暗いトイレでした。 子どもたちにアンケート調査をしたところ、学校ではトイレに行くのを我慢すると答えた子どもが少なくなかったのです。我慢する理由はトイレが汚いこと、くさいことが大きな要因となっていました。 排泄を我慢するのは健康上も問題であるこ … 続きを読む 便育コラム 第19回学校でトイレに行けない症候群
0歳や1歳の子どもでは排泄を恥ずかしいと思う感覚はまだありません。恥ずかしさの感覚は養育環境に影響されながら形成されてゆくものです。 保育園や幼稚園のトイレは男女を区別せずに設置しているところが大変多く、5歳児が使うトイレでも間仕切りが無く一つ一つの便器が個室になってない場合も珍しくありません。 ある保育園で園舎の改修に伴って、間仕切りの無いトイレから間仕切りをつけて便器を個室に改修したところがありました。 … 続きを読む 便育コラム 第18回いつから排泄がはずかしくなるの?
子どもが言葉を達者に使えるようになると、「うんち・おちんちん・おしり・おっぱい」など排泄に関することばや性に関する言葉を多用してふざける行動がよくみられるようになります。 きょうだいや友達同士で下ネタを言い合って、いつまでもふざけている姿はよくみかけますね。このようなことは特に男の子同士でよくみられます。 なぜこの時期の子どもたちは排泄に関する言葉や性に関する言葉でこんなに笑いあって盛り上がるのでしょうか。 … 続きを読む 便育コラム 第17回子どもは下品なことばや下ネタが大好き!
保育園のトイレを子どもたちが自由にアクセスできるようにすると、どんな変化があるのでしょうか。 「第15回 自由にトイレに行けると自立が早くなる!」でご紹介した大阪のおおわだ保育園の1・2歳児クラスのトイレでの事例を見てみましょう。 2歳児は以前は汽車のように隊列を組んで一斉にトイレの中まで行きましたが、改修後は子どもたちのペースでトイレに行くようになりました。 急いでいる子はさっさと便器に座り、 … 続きを読む 便育コラム 第16回子どもたちが自分で考えて調整する環境
大阪の門真市にあるおおわだ保育園の1・2歳児クラスのトイレを改修させていただきました。 改修前は保育者が子どもと一緒にトイレに付いていかなくては安全に用を足させることはできませんでした。 なぜなら保育室とトイレは重たいサッシで区切られていましたし、トイレの中はサンダルに履き替えなくてはならず、子どもに触わってほしくない汚物流しや掃除道具などいろんなものが置いてあったからです。 また限られた保育者 … 続きを読む 便育コラム 第15回自由にトイレに行けると自立が早くなる!
埼玉県さいたま市の浦和ひなどり保育園では0・1歳児保育室のトイレを園舎改築の折に保育室の中に設置しました。 改築前も保育室とトイレは引き戸一枚でつながっていましたが、トイレを使うことはありませんでした。 なぜならトイレの中に入ると保育室からは死角になって子どもから保育者の姿を見ることができず、保育者も子どもの姿を確認できないので一人でトイレに行かせることはできなかったからです。 それで当時は「お … 続きを読む 便育コラム 第14回子どもが主体的になれるトイレタイムを
保育園のトイレ環境について調査(関東圏の保育園144箇所)したことがあるのですが、0歳児クラスの保育室に「トイレ環境が無い」またはトイレが保育室に隣接しておらず廊下を経由しないとトイレに行けないなど「保育室からトイレに直接出入りできない」という園は約45パーセントありました。 これは何を意味しているのでしょう。 0歳児クラスの子どもたちはトイレを使わないという前提で保育を行っている園が少なくないということです … 続きを読む 便育コラム 第13回保育園の0歳児室にトイレがないのはなぜ?
おむつが取れれば、交換する手間がなくなるし、外出時の荷物も減るし、家の中も片付くし・・・・と思うと、早く取りたいと考えるのは当然のことですね。 このおむつに関する手間から早く逃れたいという気持ちを後押ししている要素の一つにうんちへの嫌悪感があります。 おむつを交換するには手や衣服が汚れたりすれば、ニオイも臭いです。 子どものおしりからうんちのニオイが漂って、おむつを交換する必要が生じたと認識した … 続きを読む 便育コラム 第12回子どものうんちがだんだん嫌になる
おむつからパンツに移行する途中で、子どもがお漏らししちゃうのは当たり前のことです。 今までずっとおむつをつけられて、その中で用を足すことを強いられてきたのに、急に「おむつを卒業しましょう」と言われて、すぐに上手にトイレでできるようになるわけがないのです。 中には運よく移行がスムーズに進んで、お漏らしをほとんどしないでおむつを卒業する子どももいるかもしれませんが、それは稀なことでしょう。 私は若い … 続きを読む 便育コラム 第11回おもらしは「失敗」ではない
「トイレットトレーニング」という言葉は、ある時期に必ずやらなくてはならないというイメージがあり、親たちを急き立てているような気がして、私は好きになれません。 そして「トレーニング」の結果として使われる言葉が「成功」や「失敗」であり、やり方が「良い」とか「悪い」とか子育てを評価することにつながっていくのではないでしょうか。 一方、子どもが食べ物をうまく食べられるようになっていく過程で「トレーニング」という言葉を … 続きを読む 便育コラム 第10回トイレットトレーニングって誰のトレーニング?
保育園ではできているのに、家に帰ってくるとできない、ということがよくあります。 保育園ではひとりで着替えられるのに、家では手伝わないと服を着られないとか、保育園ではさっさとできるのに、家ではグズグズしてなかなか進まないとか。 連絡帳で「〇〇がひとりでできるようになりました」と先生がお知らせしてくれるのだけれど、家ではどうもそんなにうまくいかないということは、自立するちょっと前によくおこるようです。   … 続きを読む 便育コラム 第9回保育園ではできるのに、家ではできない
あるご家庭の親子の様子を観察させていただいたときのことです。 お父さんとお母さんと2歳半ぐらいの男の子がリビングで休日の午前中を過ごしていました。 男の子は一人でおもちゃに向かって遊んでいますがなんとなく手持無沙汰な様子です。 「パパ!」とお父さんを呼んでみますが、お父さんは新聞を読みながら「うん?」と言うだけで男の子のほうを見もしません。 お母さんはパソコンに向かって何やら熱心に … 続きを読む 便育コラム 第8回「うんち!」で大人を試す
一旦、おむつを卒業できたのに、またお漏らしに逆もどりしてしまうことがあります。 特に妹や弟が生まれたタイミングで起こることも多いです。 このような場合の「おむつ返り」は「赤ちゃん返り」の一つの現れ方です。 今まで両親の愛情を独占してきたのに、強力なライバルが現れたわけですから、子どもにとっては人生最大の危機的な状況だといえるでしょう。 排泄だけでなく、着替えなど生活全般に赤ちゃん返 … 続きを読む 便育コラム 第7回おむつ返りはどうして起こる?
子どもって、うんちをトイレに流すときに「バイバーイ!」ってすることが多いですよね。 「バイバイ」してすぐに便器から離れる子ども、うんちが見えなくなってもしばらくじっと便器を見ている子どもとさまざまです。 親が「うんちにバイバイしようね」と誘いかけたことがきっかけになることもあると思いますが、この時期の子どもが花や人形などにもあいさつしたり、話しかけたりすることとも関連があるでしょう。 そしてまた … 続きを読む 便育コラム 第6回うんちに「バイバーイ!」
子どもが2歳を過ぎるころになると、「そろそろ、うちもやらなくちゃ」と焦るお母さんもいれば、「最近はゆっくりでもいいって言うわよね」とのんびり構えるお母さんもいて、果たしてどちらが正しいのか・・・・。 「トイレットトレーニング」というと、ある時を境に急に始めるようなイメージがありますが、それも変な話です。子どもの発達は何かが急にできるようには進まないからです。 他に「おむつはずし」とか「おむつはずれ」という呼び … 続きを読む 便育コラム 第5回 「おむつはずし」と「おむつはずれ」
「おむつなし育児」が話題になっていますが、ご存知ですか? 「おむつなし」といっても、全くおむつを使わないわけではなく、おむつを使いながらも乳児期からできるだけおむつの外で排泄させるという育児方法です。 「おむつ」を使う動物はヒト以外には見当たりませんが、他の動物の赤ちゃんが汚物にまみれてしまうことはありません。ヒトの赤ちゃんも本来はおむつを使わなくてももっと早くから排泄をコントロールできるようです。 大人の都 … 続きを読む 便育コラム 第4回 おむつなし育児
考えてみれば子育てに「おむつ」を使うのはヒトだけです。犬も猫も「おむつ」を使うなんてことはないですね。ヒトの親戚チンパンジーだって使いません。(飼育下にある動物に人間がつけることはありますが) なぜヒトは「おむつ」を使うことになったのでしょうか。 それはヒトの子育てが「離れつつ保護する」という独特の方式をとっているからです。 ヒトの子育てが他の動物と決定的に違っていることはさまざまな「モノ」が母 … 続きを読む 便育コラム 第3回 なぜヒトは「おむつ」を使うのか?
お母さんが家庭でオムツを交換する場合と、保育士さんが保育園でオムツを交換する場合を比較したことがあります。 お母さんが子どもの「うんちサイン」を受け止める方法はとっても多様です。 モジモジする子どものしぐさや、重たそうなオムツの形や、においや、オムツの中を触った感触や、子どものぐずりや子どもからの申告など、実にいろいろな情報を、目で見て、鼻で嗅いで、耳で聞いて、手で触って、うんちが出ていないかどうかを確認しよ … 続きを読む 便育コラム 第2回 お母さんは「うんちサイン」を五感でキャッチ
赤ちゃんのオムツを開いて、うんちを発見した時、どんなリアクションをしていますか? 「げっ、くさーい!」とか、 「あ~あ、またうんちだ」などと、 鼻をつまんだり、顔をしかめたりしますか? それとも 「おっ!うんちがでたね~」とか、 「わお!りっぱなうんちですね~」などと、 にっこり笑いながら赤ちゃんに話しかけますか? 赤ちゃんはお母さんからオッパイや食事を受け取りますが、実は「うんち」は赤ちゃんか … 続きを読む 便育コラム 第1回 うんちはプレゼント!
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 (お悩み) 『子どもがテレビを見ている間は静かなので、ついついテレビに子守をさせてしまいます。テレビはやっぱり子どもに悪影響を与えてしまうのでしょうか?』 スマホが親子のコミュニケーシ … 続きを読む 第21回「テレビとの上手な付き合い方」編3
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 (お悩み) 『子どもがテレビを見ている間は静かなので、ついついテレビに子守をさせてしまいます。テレビはやっぱり子どもに悪影響を与えてしまうのでしょうか?』 子どもは二つのことに集中でき … 続きを読む 第20回「テレビとの上手な付き合い方」編2
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 (お悩み) 『子どもがテレビを見ている間は静かなので、ついついテレビに子守をさせてしまいます。テレビはやっぱり子どもに悪影響を与えてしまうのでしょうか?』 テレビの見せすぎは、言葉の発 … 続きを読む 第19回「テレビとの上手な付き合い方」編1
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 絵本は、親から子へ受け継ぐ「心の栄養」 読み聞かせをするときは、テレビを消して、子どもがお母さんの声に集中できるようにしましょう。 何より絵本の読み聞かせは、お母さんと子ど … 続きを読む 第18回「絵本でこころの栄養補充」3
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 4歳になると物語世界を楽しめるように ただし、4歳になったら解説を加えずに、絵本の文章だけを読み聞かせるようにしましょう。そのほうが、集中して一つの物語世界を頭の中で構築で … 続きを読む 第17回「絵本でこころの栄養補充」2
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 赤ちゃんには「読み聞かせ」ではなく、本と「遊ぶ」感覚を大切に 絵本は0歳の赤ちゃんから大人まで、誰もが楽しめるものです。赤ちゃんにとって、絵本と出会うのはとてもうれしい経験 … 続きを読む 第16回「絵本でこころの栄養補充」1
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 お母さんは、子どもの苦手を応援するサポーターに 『うちの子は一人遊びが好きで、友達の輪に入っていこうとしません。どうしたら、友達となかよく遊べるようになるでし … 続きを読む 第15回 「図鑑型」の子どもと「物語型」の子ども 編3
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 「もの」に興味のある【図鑑型】。「ごっこ遊び」が好きな【物語型】 たとえば図鑑型の男の子は、外でみんなとヒーローものの遊びをするより、家で積み木遊びをしたり、 … 続きを読む 第14回 「図鑑型」の子どもと「物語型」の子ども 編2
―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がやさしく解説してくださいます。 脳の発達の段階に応じた、折々の子どもの姿がわかると、 子育ては一層たのしいものになることでしょう。 子どもにはそれぞれ、もって生まれた「気質」「性格」があります。 以前、私の研究室で、生後10か月の赤ちゃん80名を対象にして、犬型ロボットのアイボを使った研究 … 続きを読む 第13回 「図鑑型」の子どもと「物語型」の子ども 編1
知って納得!子どもの脳の成長編 親がいくら教えても、子どもがその通りにできない時はできないものです。 子どもが親の言うことを聞かないのにも理由はあります。親にとってはマイナスに思えることも、 実は子どもが成長していくための大切なプロセスでもあるのです。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がや … 続きを読む 第12回 子どもの成長は一進一退。焦らず見守りましょう
知って納得!子どもの脳の成長編 親がいくら教えても、子どもがその通りにできない時はできないものです。 子どもが親の言うことを聞かないのにも理由はあります。親にとってはマイナスに思えることも、 実は子どもが成長していくための大切なプロセスでもあるのです。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がや … 続きを読む 第11回 物事のルールがわかるのは5歳から
知って納得!子どもの脳の成長編 親がいくら教えても、子どもがその通りにできない時はできないものです。 子どもが親の言うことを聞かないのにも理由はあります。親にとってはマイナスに思えることも、 実は子どもが成長していくための大切なプロセスでもあるのです。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がや … 続きを読む 第10回 2歳頃から多くなる「独り言」。思考が育っている証拠です。
知って納得!子どもの脳の成長編 親がいくら教えても、子どもがその通りにできない時はできないものです。 子どもが親の言うことを聞かないのにも理由はあります。親にとってはマイナスに思えることも、 実は子どもが成長していくための大切なプロセスでもあるのです。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 今回は、子どもの「脳の育ち」を軸に、子どもの成長のプロセスを 内田先生がや … 続きを読む 第9回 男の子脳・女の子脳の違い
子どもが子どもでいられる時間は長いようで、とてもみじかいものです。 「いい親」になろうとがんばりすぎず、焦らず、 お子さんと一緒に1歩ずつ、楽しみながら進んでください。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より) ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―「楽習」 与える「おもちゃ」は少ないほうが「集中力」が育ちます! おもちゃで遊んでいてもすぐに飽きてしまう、次々に違うおもちゃで遊んでいる……こ … 続きを読む 第8回 「1~2歳児のママへ」編4
子どもが子どもでいられる時間は長いようで、とてもみじかいものです。 「いい親」になろうとがんばりすぎず、焦らず、 お子さんと一緒に1歩ずつ、楽しみながら進んでください。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より) ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―「楽習」 好奇心を育てる4つのルール「待つ・見守る・急がない・急がせない」 最近、砂場が汚いから遊ばせたくないという親御さんが増えているようです … 続きを読む 第7回 「1~2歳児のママへ」編3
子どもが子どもでいられる時間は長いようで、とてもみじかいものです。 「いい親」になろうとがんばりすぎず、焦らず、 お子さんと一緒に1歩ずつ、楽しみながら進んでください。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より) ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―「楽習」 させてますか?「泥んこ遊び」 感性を磨く大事な遊びです。 最近、砂場が汚いから遊ばせたくないという親御さんが増えているようですが、子ど … 続きを読む 第6回 「1~2歳児のママへ」編2
子どもが子どもでいられる時間は長いようで、とてもみじかいものです。 「いい親」になろうとがんばりすぎず、焦らず、 お子さんと一緒に1歩ずつ、楽しみながら進んでください。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より) ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ―「楽習」 コミュニケーション力を育てたいなら「ごっこ遊び」を一緒に楽しんで! 子どもは1歳半くらいで、おもちゃのお茶碗にご飯を入れて食べるまねや … 続きを読む 第5回 「1~2歳児のママへ」編1
子どもにとって、親はかけがえのないものです。 特別なことをしなくても、子どもと一緒に笑い、泣き、考え、 行動するという時間を共有するだけで、子どもはぐんぐん成長していきます。 子育てとは、とても自然なものなのです。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より) ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 前回までは「楽習」について内田先生に語っていただきました。 今回は「楽習」の土台ともいえる、赤ちゃんとお母さん … 続きを読む 第4回 「赤ちゃんとお母さん」編2
子どもにとって、親はかけがえのないものです。 特別なことをしなくても、子どもと一緒に笑い、泣き、考え、 行動するという時間を共有するだけで、子どもはぐんぐん成長していきます。 子育てとは、とても自然なものなのです。 (内田伸子先生著書『子育てに「もう遅い」はありません』より) ―たのしく・あそぶ・まなぶ・そだつ― 前回までは「楽習」について内田先生に語っていただきました。 今回は「楽習」の土台ともいえる、赤ちゃんとお母さん … 続きを読む 第3回 「赤ちゃんとお母さん」編
「子どもたちが、『やってみたい!』と思うようなことをできるだけたくさんさせてあげればいいのです。小さいうちに、多くの楽しい経験をさせてあげればいいんです。そうすれば、もし知らないことに向き合ったときにも、物怖じせずに『何だろう? やってみよう!』と意欲につながる。 『知らないことを知るのは、楽しいんだ』と経験的に知っている子は、生きていく上でとても強いですよ。 ところで、子どもたちがしたいこと、大好きなことって、何だと思います? ……そ … 続きを読む 第2回 「楽習」主体的な遊びを通して 子どもは伸びる2
長年、教育の現場で多くの子どもたちとふれあい、 数々の調査研究を行われてきた内田先生。 今、日本の子どもたちに必要なものは、 “楽習”であるとお話ししてくださいました。 耳慣れない、この言葉。 いったい、どのようなものなのでしょうか? 子どもの学びにおいて、何よりも大切なこと。それは、〝主体性をもたせる〞ことだと話す内田伸子先生。「〝主体性〞などというと、少し難しく感じるかもしれませんね。言い換えれば、重要なのは〝play … 続きを読む 第1回 「楽習」主体的な遊びを通して 子どもは伸びる




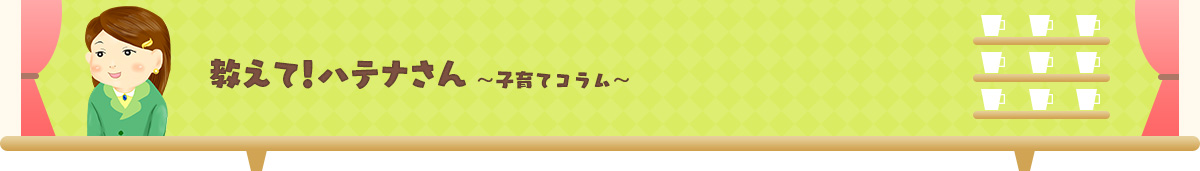
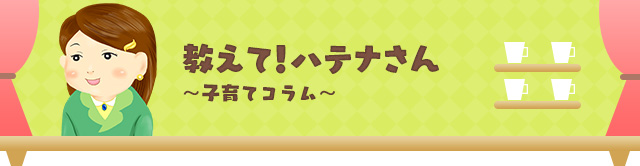

 [第1回~第21回執筆者]
[第1回~第21回執筆者]